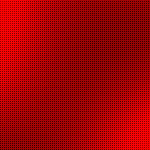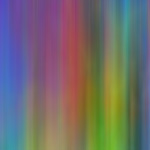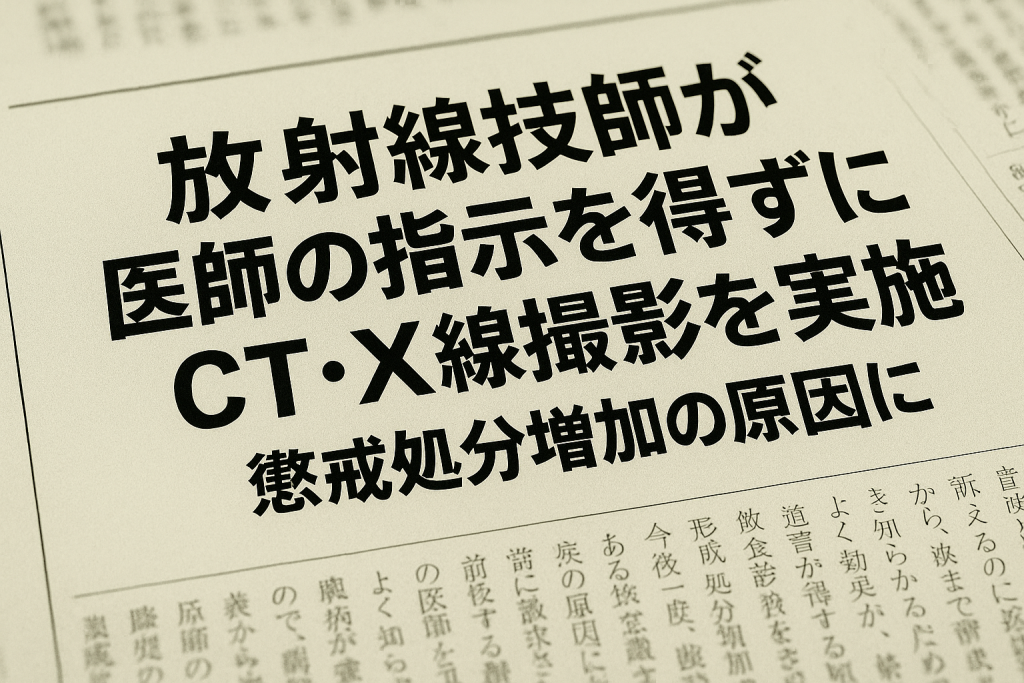
近年、診療放射線技師が医師の指示を得ずにCTやX線撮影を行い、懲戒処分を受ける事例が複数報道されています。今回、これらの事例が発生する背景や原因について実際の事例、医療現場の状況から詳しくみていきたいと思います。
目次
技師の法律で定められた業務範囲と遵守義務
診療放射線技師法第26条では、技師が放射線を照射するには医師の具体的な指示が必要であると明記されています。この法律に違反した場合には刑事罰(懲役または罰金)が科される可能性もある厳格なルールです。健康診断などで例外的に医師の立ち会いが不要な場合もありますが、それも事前の承認と条件整備が必要で、技師の完全な独断による撮影行為は重大な法令違反となることをまずはしっかりと認識してください。
無断撮影による懲戒処分事例の報道と判例
医師の指示を得ずに放射線検査を行った診療放射線技師が懲戒処分を受けた事例は、近年各地で報道され増加傾向にあります。以下の主な事例を見ていきましょう。
2012年(秋田県):診療放射線技師2名が、医師に無断で知人や自分自身にX線・CT検査を行っていたことが発覚しました。一人は義父の腹部CTや知人の手のレントゲン撮影を無断実施し、「頼まれて断れなかった」と違法と認識しつつ応じていたとされています。もう一人も独断で自分の膝にX線を当てていたことが判明しました。この件で、男性技師(39歳)は停職3か月の懲戒処分となり、女性技師(36歳)も後日戒告等の処分を受けています。病院長は「法令順守意識の欠如と放射線の危険性に対する認識不足によるもので遺憾」と陳謝しています。
2014年(愛知県):診療放射線技師が医師に無断でCT検査やX線撮影を行った事例があり、病院から懲戒処分を受けています。
2018年(千葉県):男性放射線技師が、夜勤中に女性同僚職員の「腹痛が続く」という訴えに対し、医師の指示なく独断でCT検査を実施した事例があります。幸い女性職員に健康被害は確認されませんでしたが、この行為は診療放射線技師法違反の違法な医療行為です。しかし病院は当初公表せず、情報提供を受けた千葉県が2021年に口頭指導する形で対処しました。
2022年(広島県):診療放射線技師の男性職員2名が医師指示なしにCT検査を実施し、戒告の懲戒処分を受けました。一人の技師が息苦しさ等の体調不良を感じ、自身の胸部CTを同僚技師に依頼して撮影させたものです。この不正行為は、後日その技師が別の医療機関を受診した際に自分で撮ったCT画像をスマートフォンで見せて紹介状作成を依頼したことで発覚しました。紹介状に「市民病院でCT撮影」と書かれていた。病院は2名を懲戒処分にするとともに、本件を診療放射線技師法違反の疑いで県警に刑事告発しましたが、最終的に不起訴処分となっています。
2023年(大阪府):診療放射線技師20名もの大規模な違反行為が判明しました。複数の技師が自分や同僚の健康状態を確認する目的で医師の指示なくX線・CT検査を行い、発覚を恐れて画像データを削除するなど隠蔽工作も試みていました。2022年7月に匿名の情報提供があり調査したところ、過去に遡って多数の技師の関与が明らかになったものです。この不正に対し、同センターでは課長級の技師1名を停職7日、課長補佐級1名を減給1か月、他にも数名を減給処分、残りの十数名を戒告処分とするなど合計20名に懲戒処分を科しました。
大阪急性期・総合医療センターの診療放射線技師に懲戒処分 – 医療アラウンドから要約
詳細な調査報告によると、ある50代技師長は医師の指示があるよう装って部下に自分のレントゲンを撮らせ、データIDを改ざんする、別の技師は部下から依頼された無指示のレントゲン撮影に応じデータ削除にも関与するといった組織的隠蔽も発生していました。また、自己の疾病確認のため度重なる無断CT撮影を行った例や、機器の性能テストのためと称して無指示で撮影した例も含まれており、一部では医師の指示を偽装する悪質な手口も確認されています。
この事例は非常に多数の職員が関与した点で特異ですが、裏を返せば一部組織では法令違反への認識が極めて甘く、同僚同士で違法行為を黙認し合う風土があったことを示しています。
2025年(岩手県):診療放射線技師の延べ10名が、過去数年にわたり医師の指示を得ずに放射線機器を不適切使用していたことが明らかになりました。2024年6月に59歳の技師が自分の病気を調べるため同僚にMRI撮影を依頼して無断検査したことが発端となり、その調査の過程で2015年には自分の子どものためにレントゲン撮影、2020年には同僚職員の病気確認目的でレントゲン・CT撮影、2009年及び2019年には資料作成や装置設定確認のために自分の身体でCT撮影するなど、複数の不正事例が判明しました。岩手県はこれら計10名に対し、59歳技師長と53歳技師長を減給1か月、そのほか5名を戒告(いずれも同僚・子ども関連の無断検査)、残る2名(自分の子供・自分自身を撮影した事例)にも戒告処分としています。いずれのケースでも撮影を受けた職員や家族に健康被害は報告されていないとのことですが、明確な法令・服務違反として厳正に処分されています。岩手県医療局は「二度と発生しないよう綱紀保持を徹底する」とコメントしています。
本人や同僚、子どもの病気調べる目的でMRIやCTなど撮影 県立病院職員10人を懲戒処分 医師の指示得ず放射線機器を不適切使用 岩手 | IBC NEWS | IBC岩手放送 (1ページ)から要約
以上のように、技師が無断で放射線検査を行った事例は各地で散発的に起きており、近年はそれが続けて報道され「事例が増加している」印象を与えています。
背景要因とは? 人員不足・業務過多・医師不在の現場状況
こうした技師の違法行為が起きる背景には、医療現場の人的・組織的な問題も指摘されています。特に地方や夜間などで医師が常時その場にいない状況や、スタッフの不足・業務過多が影響している可能性があります。
一例として、医療法規上は本来医師の立ち会いが必要な検診業務(バリウムを用いた胃部X線検査など)において、地方の医師不足から長年にわたり医師不在で検査を続け違法状態になっていたケースがあります。島根県では、胃がん集団検診車に医師が同乗せず違法状態が常態化していたため、県が改善指導を行ったと報じられました。背景には深刻な地方の医師不足があるとされています。(医師の立ち会いなしで胃X線、長年違法状態 背景に地方の医師不足 [島根県]:朝日新聞)
このように医師リソースが足りない現場では、本来なら医師が行うべき判断・立ち会いが十分になされず、現場の技師が規則を逸脱せざるを得ない状況に追い込まれる場合があります。同様に、夜間・救急の現場では当直医が非常勤であったり少人数で多数の症例に対応していることから、逐一医師の指示を仰ぐ手続きが形骸化しやすい環境があります。実際、前述の千葉のケース(2018年)では夜勤帯に医師に連絡せず技師の判断で同僚にCTを実施しており、これは「緊急時に医師を呼ぶより自分たちで対処してしまおう」という心理や、医師不在時間帯に患者(この場合は同僚)の状態を確認したいという切迫感が影響した可能性があります。医師が病院に不在でも電話指示を仰ぐ手段はあったはずですが、深夜であったことなどから「確認だけなら…」という甘い判断が生まれたのかもしれません。
また、診療放射線技師自体の不足や多忙さも間接的に関与する可能性があります。例えば一人当直の技師が多くの検査業務に追われていると、逐一医師のオーダー書発行を待つ手間を省いてしまおうと考えるリスクが高まります。大阪の事例では多数の技師が違反行為に関与していましたが、裏を返せば「忙しい業務の合間に自分の健康不安を感じても、医師にかかる暇がないので職場の装置で検査してしまう」という心理も働いた可能性があります。このように業務量の多さや人手不足による心身の余裕のなさが、法令順守より目先の利便性を優先させる要因になりえます。
さらに、組織としてのガバナンスや監督不足も背景にあります。通常、放射線検査の実施には検査予約やオーダーシステムで医師承認が必要ですが、内部者同士の口頭依頼で検査が行われ、かつそれが院内で見過ごされていた状況があります。大阪のケースでは長年にわたり多数の違法検査が行われていましたが、画像データを削除するなどすれば発覚しにくい体制だったことになります。病院側の監査体制が不十分だと、技師同士のなれ合いによる隠れた撮影が起きやすくなります。
つまりは医師側のリソース不足(不在・過少)、技師側の人員不足や過重労働、そして組織内の監督体制の甘さが重なると、診療放射線技師が本来のルールを破ってでも現場を回そうとしたり、自己や周囲のニーズに応えてしまったりする土壌が生まれます。その結果として無断撮影が発生・黙認され、問題が潜在化してしまうのです。
教育・研修制度の不備と現場ルールの曖昧さは?
違法行為に手を染めてしまう背景には、法令順守や倫理に関する教育・研修の不徹底**もあると考えられます。多くの事例で技師は「違法と知りつつ行った」ことを認めており、規則そのものは理解していたようですが、それを実践で守る意識が希薄でした。このことは倫理教育の不足や現場ルールの形骸化を示唆します。
たとえば千葉県のケースでは、発覚後に病院が再発防止策として放射線室の運用マニュアルを掲示したものの、同じ職場の職員は「病院から何か説明を受けた記憶はない」と証言しています。(サイエンスニュースまとめ☆ななめ読み : 放射線技師が無断でCT検査、違法行為だが病院は公表せず)
実際、違法行為発覚翌月(2018年12月)に院内の一室ドアにマニュアルを貼り出しただけで、職員への周知徹底は図られなかった模様です。このように形式的な対策に留まり、現場スタッフへの教育・共有が不足すると、規則はあっても「知らなかった」「気付かなかった」という言い訳を許す環境になってしまいます。
また、診療放射線技師の養成課程や新人研修においても、法的遵守や倫理観の醸成が十分であったか再検討が必要です。法律上禁止されている行為であるにもかかわらず、「同僚に頼まれて断れなかった」、「機器のチェックのつもりだった」 といった技師側の言い分が出てくるのは、職業倫理教育の弱さや現場でのルールの曖昧さの表れです。言い換えれば、「患者(または検査対象者)の安全と法令遵守を最優先にすべき」という基本原則が徹底されていなかったことになります。
さらに、物理的な研修機会や設備不足も指摘できます。機器の調整や練習を行う際に、本来はファントム(模擬人体)などで行うべきところを自分の体で試してしまうという事例が見られました。これは現場で「それぐらい問題ない」という安易な風潮があったか、あるいは研修設備(ファントム等)が十分用意されておらず安直な手段に流れた可能性があります。こうした現場ルールの不明確さ(何が厳禁で、どう対応すべきかの指針不足)は、技師が違法行為に手を染める土壌となり得ます。
大阪の大規模不正では、技師長クラスが率先して隠蔽に関与していたことから、組織のトップからして倫理意識が欠如していたことが伺えます。このような環境下では部下も違法行為への抵抗感が薄れ、「皆がやっているから」という状態に陥ります。内部告発があるまで是正されなかった組織風土自体、教育・遵法意識の欠如を物語っています。
以上より、現場レベルでのルール周知と教育(研修)不足、そして倫理綱領の形骸化が無断撮影を許していた一因と考えられます。各医療機関は違反発覚後にマニュアル整備や聞き取り調査を実施していますが、それが実効性を伴う形で全職員に理解・浸透しているかが重要です。
関係学会・医療機関によるガイドライン・注意喚起はどうなのか?
相次ぐ不祥事を受けて、関係団体や医療当局も診療放射線技師による違法行為防止に向けた注意喚起やガイドラインの再確認を行っています。
日本診療放射線技師会は、2025年1月29日付で「放射線機器の適正利用と倫理意識の向上について(会員各位への依頼)」という文書を公表しました。そこでは「先日、複数の診療放射線技師による放射線画像診断機器の不正使用に関する報道があった。医師の指示なく、自身の病気の確認を目的として同僚に依頼しCT検査を受けたことなどが明らかになった」と、最近の事例に直接言及しています。その上で「このような行為は診療放射線技師としての倫理に反するだけでなく、放射線の安全利用の観点からも決して許されない。放射線の人体への照射は医行為であり、診療放射線技師が信頼され業務を与えられていることを改めて強く認識するよう」求めています。会員に対し今一度法令遵守の徹底と、技師会が定める倫理綱領の再確認、高い倫理観と責任感を持った業務遂行をお願いする、という厳しい内容で、われわれ技師に向けた注意喚起となっています。このような公式声明は異例とも言え、技師会自らが率先して綱紀粛正を図る姿勢を示したものです。
まとめ
最後に、今回の一連の問題から得られた教訓として、組織ぐるみの注意喚起が重要です。単に法規を示すだけでなく、現場の全員が「なぜそれが禁止されているのか」を理解し共有する必要があります。被ばく低減の原則、医師の診療責任の所在、患者・職員の安全文化――これらを再確認するためのガイドライン遵守が呼びかけられている状況です。各地の医療機関や技師会による注意喚起が奏功し、違法な無断撮影が根絶されることが期待されます。
放射線技師.com