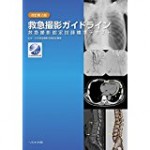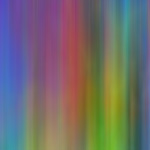ほぼ知識ゼロからのスタート
大学病院にいた頃、バリウムを用いた胃X線検査は、ほとんどやったことがありませんでした。そして、大学病院から検診業界に転職して、胃X線検査を教わりました。検査を始めてから1年経たずして、職場からの命令で胃がん検診の試験を受けることになりました。
スポンサーリンク
受験すると決めたら
申し込み期限が早いので注意してください!
今年(平成28年)の試験は9月4日でしたが、申請書類の請求期限が早いです。同じ職場の先輩は去年請求期間を逃して、今年一緒に受験しました。2月8日~3月7日までに請求して、申請書類を4月25日までに郵送しなければいけません。受験料は1万円です。
提出画像の準備
資格審査は当日行う筆記試験と技能検定試験です。技能検定試験では胃X線検査画像を提出します。アナログフィルムまたはソフトコピー画像での提出で、今年からDR装置で撮影された画像は、ソフトコピー画像での提出になったそうです。
提出画像は対策型検診の基準撮影法1か、任意型検診の基準撮影法2のどちらか1シリーズを提出します。当時は基準撮影法1とか2を知らずに撮影していました。自施設では任意型だったので、そちらで提出しました。
注意すべきは撮影順序です!
実際の現場では受診者に合わせて撮影順序を変えることがあったりするのですが、提出画像の基準撮影の順序は絶対です。また、自分は提出画像のチェックを上司にしてもらったのですが、イマイチな画像が1枚でもあるとその1シリーズはアウトとなり、提出できる画像を撮るのが大変でした。
当時は胃の形が良く、動きの良い受診者がいると余計に優しくなり、ありがとうございます!と握手をしたくなるほど大変でした。提出画像の撮影は早めに取り組んだ方が良いです。画像が決まれば勉強の方にも身が入ります。
筆記試験
筆記試験は5択のマークシート形式
解答時間は100分
画像10問を含む、計50問でした。
使用テキスト
試験勉強で使用したテキストを紹介します。
・胃がんX線検診 技術部門テキスト 2016年度版
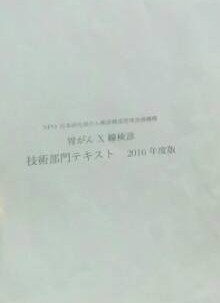
・新・胃X線撮影法ガイドライン 改訂版(2011年)
 |
新品価格 |
![]() この2冊のテキストは試験の2か月くらい前にNPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構から送られてきます。特に胃がんX線検診 技術部門テキストを熟読すれば筆記試験は通ると思いますが、教科書をひたすら読むというのが苦手な私は練習問題を解きました。
この2冊のテキストは試験の2か月くらい前にNPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構から送られてきます。特に胃がんX線検診 技術部門テキストを熟読すれば筆記試験は通ると思いますが、教科書をひたすら読むというのが苦手な私は練習問題を解きました。
・胃X線検診撮影技術・読影補助 超練習問題300選
 |
中古価格 |
![]() 数多く問題を解くことによって、力が付きます。前回受けた人は、まず問題を読むのが大変だと言っていたので、このテキストで問題に慣れました。しかし解いていくと問題と答えの間違いがかなりあり、出版社に(何度も)問い合わせたところ、3週間後くらいに正誤表が送られてきました。ホームページにも正誤表を掲載するとのこと。20か所訂正されたものでしたが、他にもあると思います。かなりミスが多いテキストなので、出版社の代表取締役曰く、今後の出版はしない方針だと語っていました。
数多く問題を解くことによって、力が付きます。前回受けた人は、まず問題を読むのが大変だと言っていたので、このテキストで問題に慣れました。しかし解いていくと問題と答えの間違いがかなりあり、出版社に(何度も)問い合わせたところ、3週間後くらいに正誤表が送られてきました。ホームページにも正誤表を掲載するとのこと。20か所訂正されたものでしたが、他にもあると思います。かなりミスが多いテキストなので、出版社の代表取締役曰く、今後の出版はしない方針だと語っていました。
この問題集を重点的にやっていたのですが、日本語もおかしいところがあるので理解に苦しみ、かなり疲れさせる問題集です。文句ばかりですが、おかげで余計にインターネットで調べたり、送られてきたテキストから答えを出そうと何度も読んだりしたので、かなり勉強になりました。返品しても構わないとのことだったのですが、理解を深めるために有効だったので手元に持ってあります。
・専門技師になるための必携テキスト
 |
新品価格 |
![]() 内容が詳しく載っていて、最後に280問の問題集がついています。先ほど紹介した超練習問題300選の練習問題を解くためには、送られてきたテキストだけでは足りませんが、このテキストで補うことができました。ただ、問題を解くためだけに利用し、他の部分は全く読みませんでした。問題集を見てみると聞いたことない用語があり、難しく感じたので、見覚えのある問題をサラッとしかやっていません。多分、読影部門やA級以上の問題だと思われます。
内容が詳しく載っていて、最後に280問の問題集がついています。先ほど紹介した超練習問題300選の練習問題を解くためには、送られてきたテキストだけでは足りませんが、このテキストで補うことができました。ただ、問題を解くためだけに利用し、他の部分は全く読みませんでした。問題集を見てみると聞いたことない用語があり、難しく感じたので、見覚えのある問題をサラッとしかやっていません。多分、読影部門やA級以上の問題だと思われます。
検定試験はB、A、S級の3段階あるようですが、全員B資格から受けます。
以上4冊を使用して勉強をしました。
この試験を受けてブログに載せている人がいましたが、8冊のテキストを使用していました。
ブログはこちら(外部リンク)>>
出題傾向
意地悪な問題は出なかった
超練習問題300選の問題集を解くのに送られてきたテキストに載ってないことが多々あったので、こんなのテストに出るのかと前に受けたことある人に聞いてみたところ、「それが出るんだよ~。この問題集を解けばバッチリ」と言っていたので、どうにかして超練習問題300選の問題集を解きました。
しかし筆記試験にはあまり意地悪な問題は出てこず、送られてきた胃がんX線検診 技術部門テキストを読みまくって、新・胃X線撮影法ガイドライン 改訂版(2011年)のテキストをサラッと読めば解けると思いました。ただ私の場合は、がむしゃらに教科書を読むのが苦手なので、問題を解きながら読んでいくやり方をしました。全問解いた後に、1回だけ胃がんX線検診 技術部門テキストを全部読み試験に臨みました。
参考になるか分かりませんが、バリウムの原子番号は覚えておいた方がよいと思います。
認定技師になるには
実はこのNPO精管構が実施する試験に合格するだけでは認定技師にはなれません。試験を通ると合格証明書と資格証明書の申請用紙が送られ、いずれかを申請すれば技術B検定資格者としてNPOに登録されます。
しかし胃がん検診専門技師、いわゆる認定技師になるには合格証明書を日本消化器がん検診学会に提出する必要があります。更に、3年以上学会の会員で会費が納入されていること、総会等の出席、症例数を満たしているなどの条件が必要になってきます。証明書は5年間有効なので、この機会にお忘れなく手続してください、とお知らせに書いてあります。
合格証明書と資格証明書はそれぞれ申請登録料として1万円かかります。資格証明書は法人が資格を取得されたことを独自に証明する書式とのことで、賞状形式で送られてくるので、施設に飾って受診者にアピールすることは出来そうです。
放射線技師.com